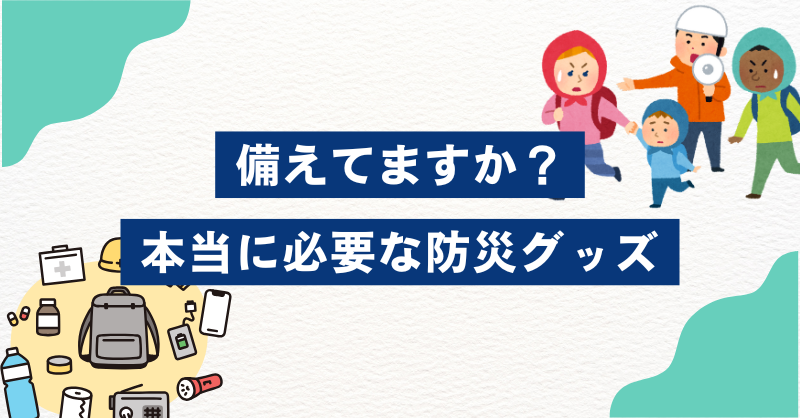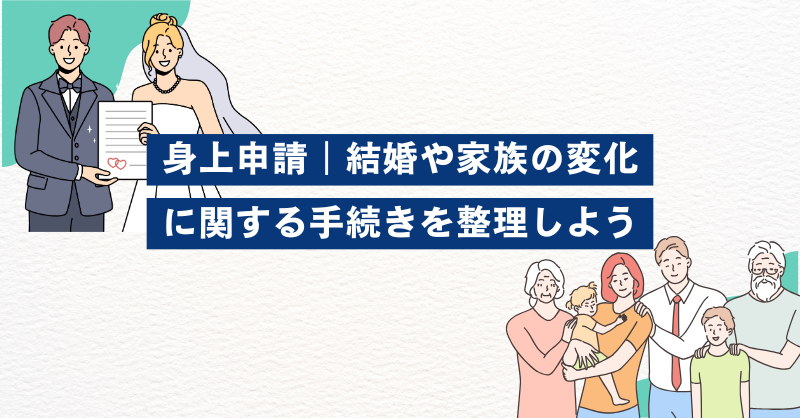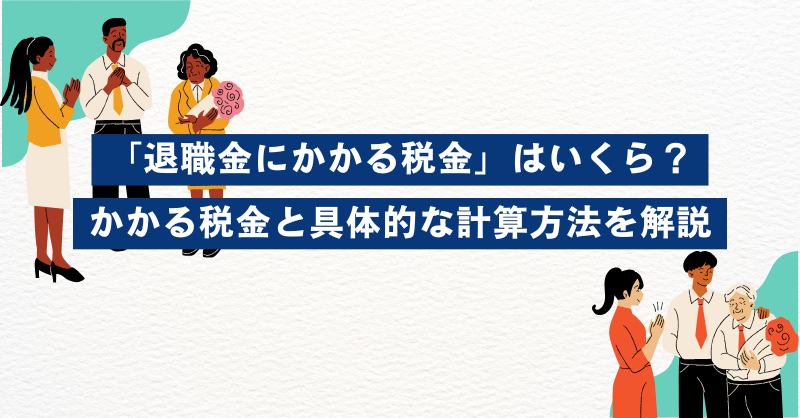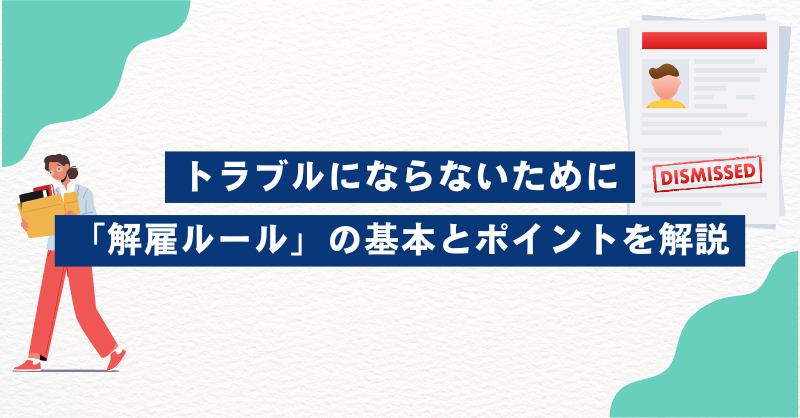日本は地震や台風、豪雨などさまざまな自然災害が多い国です。大きな災害がいつ起こるか分からないからこそ、事前の備えがとても重要と言われています。しかし、防災グッズを準備するときに「何を入れればいいの?」「どれが本当に必要なの?」と悩む方も少なくありません。
本記事では、基本セットからあると便利な防災グッズを、備える際のポイントも抑えて解説します。いざというときのために、今からしっかり準備をしておきましょう。
人事労務の最新情報や新着ブログ記事、ウェビナー情報、商品説明などをメルマガでお知らせしています。
目次
災害グッズを揃える前に
防災グッズの必要性を認識しておく
地震や台風など大規模な災害が起こると、電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまう可能性があります。特に、断水や停電が続くと飲料水や情報収集手段の確保が困難になることが多いです。こうした状況に陥ると、日常生活が大きく制限されるだけでなく、心身ともに負担がかかります。
そのため、少しでも快適に、かつ安全に過ごすために、事前に防災グッズを備えておくことが重要となります。
自宅・避難所での生活の両方を想定する
災害発生時、自宅で過ごすほうが安全なケースもありますが、災害によって自宅が大きく損壊して危険な場合は、避難所に移動する必要があります。そのため、防災グッズの準備では、どちらのパターンにも柔軟に対応できるよう、「自宅用のグッズ」と「持ち出し用のグッズ」の2種類を想定しておくと安心です。
防災グッズの基本セット
水(飲料水)
人間が生きていくうえで最も重要なのが水。調理や歯磨きなど生活用水にも使用するため、何よりも優先して準備しましょう。
必要量の目安
1人あたり1日3リットル×最低3日分=約9リットル / 人
備える際のポイント
- ペットボトル入りの水を定期的に使い回し、消費期限切れを防ぐ
- 消費期限をペットボトルのラベル、または入っている段ボールに記載しておく
- 災害時は断水や水質汚染の可能性が高いため、多めの水を備蓄する
- 夏場のときのことを考えて、スポーツドリンクも複数個用意しておく
おすすめ
非常食(保存食)
災害時、炊事の手間をかけずに食べられるものを最低3日分は用意しておきましょう。スプーンなどのカトラリーや、紙皿、割り箸などの使い捨て食器もセットで用意しておくと便利です。
具体例
- レトルト食品(カレー、スープ、おかゆ等)
- 缶詰(さば缶、ツナ缶、果物缶など)
- フリーズドライ食品(お米系、みそ汁)
- チョコレートなどの高カロリーの携帯食
- 乾パンやカロリーメイト等の栄養補助食品 など
備える際のポイント
- 高カロリーで日持ちするものを選ぶ
- 味に飽きないよう、バリエーションを持たせる
- 開封後に食べきれるサイズで用意
おすすめ
- 【Amazon.co.jp限定】 Smart Basic(スマートベーシック) アルファ米 10食セット 非常食 長期保存 5年保存 (製造から) 5種×2食 スプーン付き
- 江崎グリコ 【ビスコ保存缶】 保存食 非常食 長期保存 備蓄食 個包装 30枚
懐中電灯
夜間に災害が起こった場合、停電になる可能性が高く、明かりがない状態での移動は、思わぬケガを引き起こす可能性があります。懐中電灯を用意して、避難時にスムーズに移動できるようにしましょう。また、両手が使えるヘッドライトを用意しておくのもおすすめです。
備える際のポイント
- 可能であれば両手が使えるヘッドライトを用意
- 電池式の場合は予備の電池も用意
- 充電式なら常にフル充電しておく習慣をつける
- スムーズに避難できるように枕元近くや玄関に懐中電灯を置いておく
- 手動で発電できる懐中電灯もおすすめ
おすすめ
モバイルバッテリー
災害時の情報収集や連絡手段として使用するスマホを充電できるモバイルバッテリーも用意しておきましょう。
備える際のポイント
- 容量は10,000mAh以上を目安にする
- ソーラー充電機能付きや手回し式で充電できるものを選ぶと安心
- 定期的に充電を行い、常に充電MAXの状態にしておく
- 予備バッテリーを複数用意しておく
おすすめ
救急セット
災害でケガをした際の応急処置や感染症予防に救急セットを用意しておきましょう。
市販薬に加え、特に持病がある人は、病院に数日行かなくても大丈夫なような分の薬も備えておきましょう。
内容例
- 絆創膏、ガーゼ、包帯、消毒液、清浄綿、医療用テープなど
- 常用薬や持病薬(処方箋も含む)
- マスク、手袋、ペットボトル水(衛生対策)
備える際のポイント
- 絆創膏や消毒液など、応急処置に必要な道具が全て揃っているか確認する
- 風邪薬や解熱剤なども常備しているか確認する
- 持病がある人は持病用の薬も用意する
- 救急用の道具を一つの袋にまとめて保管する
おすすめ
防寒具・衣類
冬に災害が起こると暖房器具が使えなくなることがあり、最悪の場合、低体温症になる可能性があります。また、避難所に移動した場合、着替えを家に取りに戻ることが難しくなります。そのため、防寒具や複数の服を用意しておきましょう。
ポイント
- 防寒着やブランケット、タオル類を用意する
- 下着や靴下の替えも用意する
- 冬場のことを考えて、使い捨てカイロを備えておくと便利
おすすめ
その他の押さえておきたいもの
貴重品関連
- 現金(小銭含む)
- 預金通帳や印鑑のコピー
- 保険証コピー
- 身分証明書の写しなど
※貴重品関連は、防水ケースに入れるかジップロックなどで保護しておくのがおすすめです。
衛生用品
- ウェットティッシュ
- 汗拭きシート
- 生理用品
- 乳児用オムツ
- 携帯トイレなど
その他
- 防災用ホイッスル(※がれきの下などで救助を呼ぶ際に有効)
- 丈夫な靴(※ガラスやがれきから足を守るため)
- ペット用品(※ペットを飼っている場合)
枕元に置いておくと役立つ防災グッズ
就寝中に災害に巻き込まれることも少なくありません。暗闇や混乱の中で動き回るのは危険ですので、素早く位置を把握でき、手を伸ばしただけで届く場所に以下の防災グッズを置いておきましょう。
枕元に置いておくと役立つ防災グッズ一覧
- スマホとモバイルバッテリー
- メガネやコンタクトレンズ
- 丈夫な靴
- 懐中電灯
- 防災用ホイッスル
- 手袋
あれば便利な防災グッズ
基本セットに加えて、以下のようなアイテムがあると、災害時の生活がグッと楽になります。
ポータブル電源
ポータブル電源を持っておくと、携帯を何十回も充電できたり、小型の家電も動かすことができます。最近では、車のソケットや太陽光発電で充電できるものも増えているので検討してみてください。また、あらかじめ充電しておく必要があるため注意しましょう。
カセットコンロ
カセットコンロを持っておくと、調理やお湯を沸かす際に便利です。予備のガスボンベも忘れずに複数個用意しておきましょう。また、ガスボンベは保管期限を定期的にチェックしましょう。
手回し充電ラジオ(ライト付)
携帯式のラジオを持っておくと、スマホが使えない状況でも情報収集ができるため便利です。最近のものは多機能で、ライトが付いていたり、スマホを充電できるものもあります。手回し式で充電できるものもありますので、一つ持っておくと重宝します。
防災グッズは「見える化」と「メンテナンス」が大事
防災グッズの置き場所を家族で共有しよう
せっかく防災グッズを用意しても、いざというときにすぐに取り出せなければ意味がありません。家族全員が知っている場所(玄関近くや寝室のクローゼットなど)にまとめて保管し、「あのバッグを持って避難する」と家族内で共有しておきましょう。
定期的な点検とローリングストックの実施
災害時に、水や食料の賞味期限・消費期限が切れていたなんてことにならないためにも、年に1~2回は、防災グッズを引っ張り出して賞味期限・消費期限をチェックしましょう。非常食はふだんの食事に取り入れながら補充する「ローリングストック」が有効です。定期的に入れ替えることで、常に新しい状態をキープできます。
家族構成や季節に応じたカスタマイズを!
赤ちゃんがいる家庭はミルクやオムツ、離乳食などを多めに。高齢者やペットがいる場合は、必要なケア用品も忘れずに入れておきましょう。季節によって防寒対策や熱中症対策のアイテムを加減するなど、家族構成や季節の状況に合わせてカスタマイズすることが大切です。
防災情報の収集と災害リスクの確認
物を用意するだけでなく、情報面の準備も重要です。自治体や政府が提供している「防災アプリ」やSNSの公式アカウントを登録し、災害時の避難場所や避難経路を事前にチェックしておきましょう。また、ハザードマップを確認し、自宅周辺がどのような災害リスクにさらされているのかを理解しておくことも欠かせません。
今こそ本当に必要な防災グッズを見直そう
「防災グッズ 必要なもの」と検索すると、たくさんのリストや商品がおすすめされており、どれが本当に必要なのか悩む方も多いでしょう。しかし、優先順位を整理すれば「まずは水と食料、明かり・情報収集手段、救急セット、防寒具」といった基本の準備が必須であることが見えてきます。そこに、家族の構成や住環境を考慮して、自宅避難や避難所生活の両面で必要なものを足していきましょう。
災害はいつ、どこで起こるか分かりません。万が一に備えて、「自分と家族の命を守るために何が必要か」をしっかり考え、本当に必要な防災グッズをそろえておくことが重要です。災害が起きてから慌てるのではなく、平時の今だからこそできる準備を、ぜひこの機会に進めてください。
新着ブログ記事やお役立ちコンテンツ資料など、お得な情報をメルマガで配信しています。